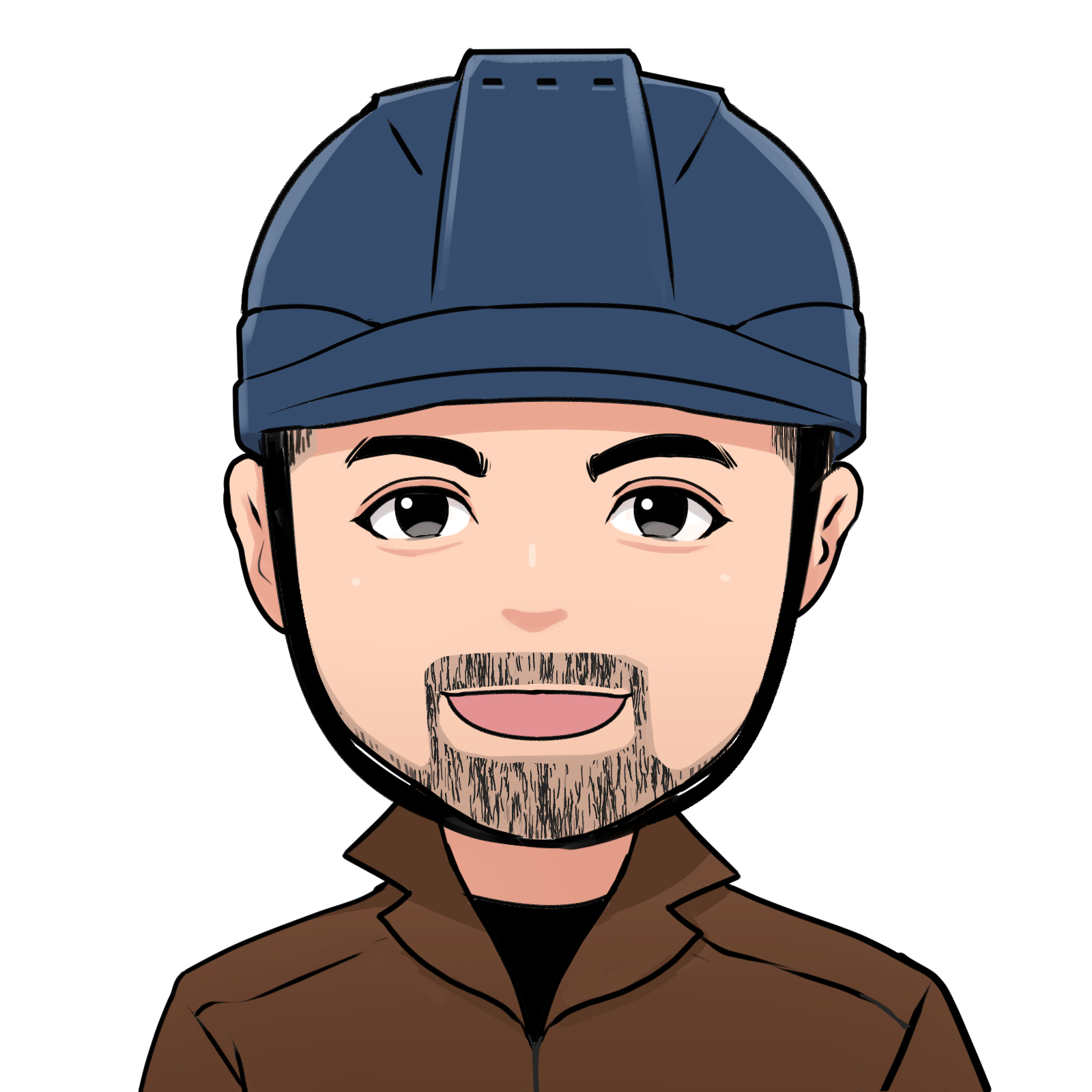
高所作業時の事故を「ゼロ」に!
株式会社G-Place 設備資材事業グループの平野です。
弊社では現場での高所事故を防ぐべく、年間のべ50件以上の現場にお邪魔し高所安全対策のご提案をしています。
このコラムでは「鳶職」に視点を向けて、安全対策を考えてみたいと思います。
ぜひご参考にしていただければと思います。
鳶職(とびしょく)は、建設現場で高所作業を専門に行う職人さんのことです。
鳶職と聞くとダボダボの作業服を着て、足場の上を軽々と動き回る姿を思い浮かべる方もいるかもしれません。
確かにそうしたイメージが根強く残っていますが、鳶職の在り方も時代とともに変化しています。
本記事では、現在の鳶職の歴史を紹介しながら、現場での危険性について解説していきます。
鳶職とは

鳶職(とびしょく)は、建設現場における高所作業を専門とし、足場の組立や鉄骨の設置、重量物の据付などの作業を担う人たちのことです。
「鳶」という名称は、高所で梁から梁へ飛ぶように移動する姿が、空を舞う鳥の「トンビ(鳶)」に似ていることに由来するといわれています。
また、作業に使われる道具「鳶口(とびぐち)」にちなむという説もあります。
鳶職の歴史は古く飛鳥時代から存在し、当時は建築に関わる職人は「右官(うかん)」と総称されていました。
江戸期に入ってから「鳶」「大工」「左官」といった職種に分化し、鳶職が一つの技能集団として認知されるようになりました。
明治時代以降は、建設業の細分化が進み、鳶職は高所作業や足場工事、基礎工事などに特化していきます。
それに伴い作業道具や足場技術も木製から鋼管・鋼材へと進化し、安全性が大きく向上しました。
現代でも「建設は鳶に始まり、鳶に終わる」といわれる通り、建設現場の始まりから終わりまでを支える欠かせない存在です。
鳶職の種類

仕事内容によっていくつかの種類に分かれており、それぞれが異なる専門技術を必要とします。
ここでは代表的な鳶職の種類を紹介します。
足場鳶
足場鳶は、建築工事や解体工事の現場で最もよく見かける鳶職です。
鉄パイプや留め具、足場板などの部材を使用し、高所作業に不可欠な足場の組立と解体を行います。
足場鳶の作業は、現場全体の安全性と作業効率に直結する重要な工程です。
鉄骨鳶
鉄骨鳶は、高層ビルやマンションなどの大型建築物で、鉄骨構造の骨組みを組み立てる鳶職です。
鳶の作業は「玉掛け(たまがけ)」と「取りつけ」に分かれます。
玉掛けは地上で資材をクレーンに取りつける作業、取りつけは高所で資材を受け取り、所定の位置に組み立てる作業です。
鉄骨鳶の作業は、建物の骨格を構築する正確性が求められる工程です。
重量鳶
重量鳶は、工場や大型施設の設備工事で、大型機械の搬入・設置を行う鳶職です。
専門性が高く、作業内容によっては特定の資格が必要になることもあります。
現場ごとに異なる重量物を扱うため、経験を積みながら技術を磨くことが求められます。
送電鳶
送電鳶は送電線の架線工事や、点検・保守作業を担う鳶職で、「送電線架線工」とも呼ばれます。
高所での作業に加え、電気に関する知識や技能も必要とされるため、電気工事士の資格が必須です。
危険度が高く、人材不足が続いている鳶職でもあります。
橋梁鳶(きょうりょうとび)
橋梁鳶は、橋梁工事の現場において、大規模な構造物の鉄骨工事を専門に行う鳶職です。
基礎工事から支保工、足場の設置までを担い、橋の構造を支える重要な工程を担当します。
現場によっては、数百メートルの高さでの作業となることもあり、常に高い危険が伴います。
体力はもちろん、冷静な判断力や集中力といった精神面での強さも求められる職種です。
鳶職に多い事故

鳶職の仕事は高所作業が中心となるため、常に危険と隣り合わせです。
ここでは、特に発生しやすい事故の例を紹介します。
転落・墜落
最も多いのは、高所からの転落・墜落事故です。
足場の組立・解体や資材の運搬中に数メートルから十数メートルの高さで作業することが多く、万が一の落下は重傷や死亡につながる危険があります。
事故原因としては、風雨などの天候条件、足場の不安定さ、安全帯(墜落制止用器具)の未使用、作業時の油断などが挙げられます。
落下物・資材の直撃
高所で使用していた工具や資材が落下し、下にいる作業員や通行人に当たる事故も発生しています。
周囲の安全確認を怠った場合や、固定が不十分な状態で作業を行った際に起こりやすくなります。
熱中症・体調不良
鳶職は屋外作業でヘルメットを着用して作業に従事するため、体温が上がりやすい環境に置かれます。
実際に、夏場では熱中症や体調不良が原因となる事故も少なくありません。
意識がもうろうとした状態では、転落や誤った判断につながる危険性が高まります。
まとめ
鳶職は建設現場を支える重要な役割を担っており、常に高所や重量物を扱う危険と隣り合わせの仕事です。
高所作業では、労働安全衛生法に基づき墜落制止用器具の使用が義務付けられており、高さ5メートル以上の作業ではフルハーネス型の着用が原則とされています。
作業に従事する皆さんは今後も安全への意識を徹底しながら、現場の土台を支える責任を果たしていきましょう。

株式会社G-place 設備資材事業グループ
📞03-3527-2992
受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
■関連ニュース記事
2024/12/10 労働新聞社
【お役立ち資料箱】高所作業のリスク再検討を 安全措置が不十分で死亡災害も 長野・松本労基署
2024/09/10 労働新聞社
適正業者登録制創設へ 安全管理の取組みを評価 墜転落災害防止で 仮設工業会
2024/08/09 労働新聞社
【トピックス】高所作業の墜落対策を確認 重点業種で好事例水平展開へ 労働局がパトロール 全国安全週間
2024/08/09 労働新聞社
足場業者に登録制度 労災減少めざし創設へ 仮設工業会
2024/06/21 RSK山陽放送
建設現場ではどんな安全対策を?労災事故が多くなるといわれる夏を前に岡山労働局が岡山市役所・新庁舎の建設現場を視察
2024/04/08 株式会社 流通研究社
厚労省、墜落制止用器具の規格不適合製品を公表
2024/01/29 日本経済新聞
西尾レント、転落防止フック未装着を検知 建設現場向け
2023/12/05 ハーバード・ビジネス・レビュー
労働者を危険から守りたければ、自社だけで安全対策してはいけない

