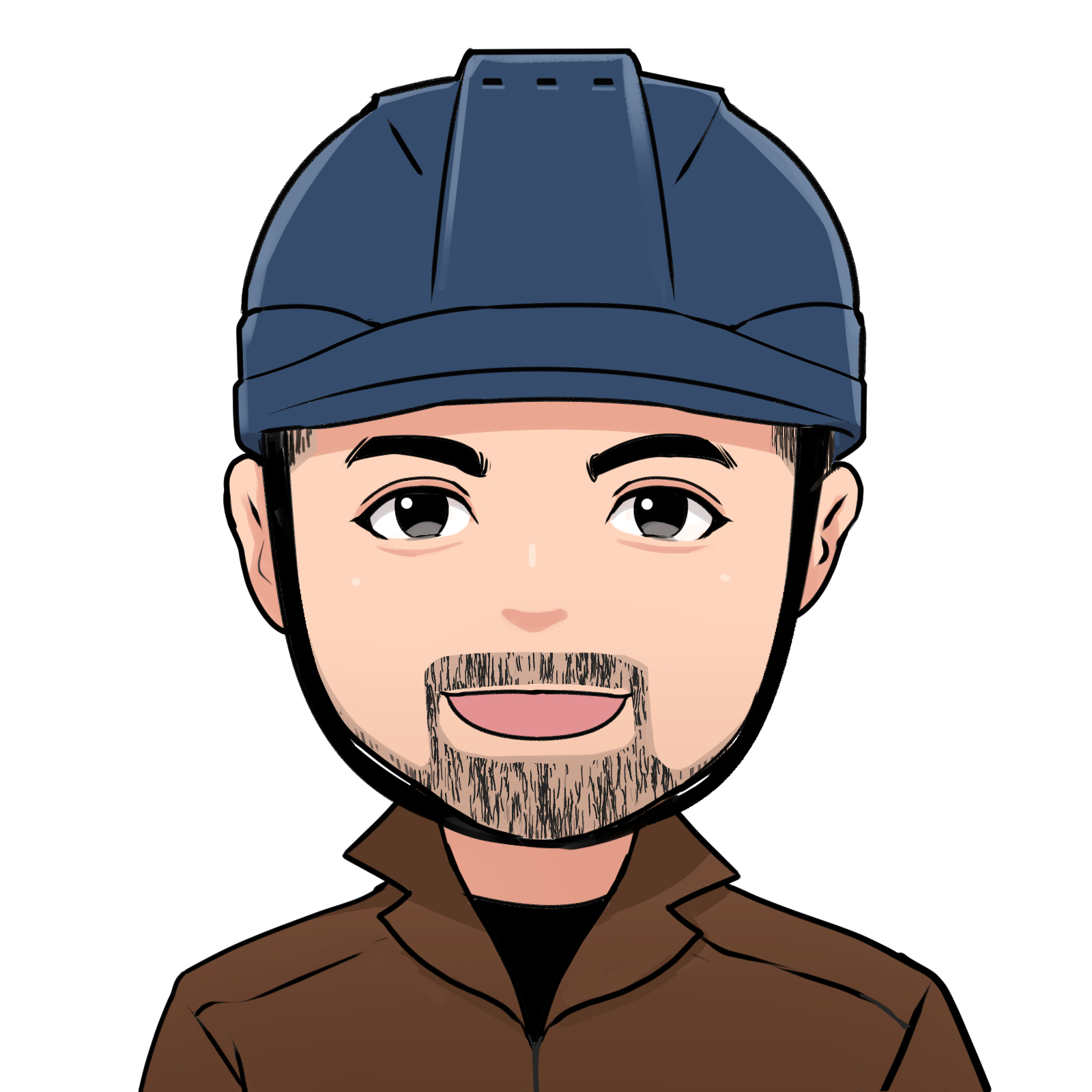
高所作業時の事故を「ゼロ」に!
株式会社G-Place 設備資材事業グループの平野です。
弊社では現場での高所事故を防ぐべく、年間のべ50件以上の現場にお邪魔し高所安全対策のご提案をしています。
このコラムでは「労働安全コンサルタント」という資格に視点を向けて、安全対策を考えてみたいと思います。
ぜひご参考にしていただければと思います。
現場の「安全」を守る専門家として注目されているのが、労働安全コンサルタントです。
高所作業などリスクが伴う職場での災害を未然に防ぐため、的確な指導や助言を行う役割を担っています。
この記事では、労働安全コンサルタントの具体的な活動内容や、資格を取得するための要件について詳しく解説します。
労働安全コンサルタントとは

労働安全コンサルタントとは労働災害を防止し、安全な職場環境を実現するために安全衛生の専門知識と経験を活かして診断・指導を行う専門家です。
事業者からの依頼を受けて職場の安全状況の把握や診断、改善計画の策定、責任者への指導、安全管理体制の構築支援などを業として行います。
労働安全コンサルタントの職務内容
労働安全コンサルタントの具体的な職務内容は以下の通りです。
- 事業所の安全状態の調査・診断、潜在的な危険や問題点の洗い出し
- 改善のための計画策定および事業所の責任者への指導や助言
- 安全に関する規則や点検基準の設定、安全衛生マネジメントシステム(OSHMS)の監査や評価
- 労働者に対する安全教育の計画・実施
- 作業手順書の作成やリスクアセスメントの指導
労働安全コンサルタントは、現場の危険箇所を指摘するだけでなく、安全衛生水準の向上を図り、法令遵守と実務的な安全対策を結ぶ橋渡し役を担っています。
労働衛生コンサルタントとの違い
労働安全コンサルタントと混同されがちな資格に「労働衛生コンサルタント」があります。
両者の最大の違いは、取り扱う分野です。
前者は墜落や転倒などの物理的リスクを中心とした「安全」に関する業務、後者は化学物質や作業環境などによる健康への影響を対象とした「衛生」に関する業務を担います。
いずれも厚生労働大臣が認定する所定の試験に合格することで、企業の外部専門家として助言や指導に従事できます。
ただし、労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントともに法定の選任義務はありません。
安全管理者や衛生管理者のような常時配置が求められる役職とは異なり、必要に応じて各事業所が自主的に依頼できる制度です。
| 項目 | 労働安全コンサルタント | 労働衛生コンサルタント |
|---|---|---|
| 対象 | 職場の「安全分野」 (機械、電気、化学、土木、建築) | 職場の「衛生分野」 (化学物質、騒音、粉じん、ストレス、熱中症など) |
| 役割 | 安全診断やリスクアセスメント 安全管理体制の構築や指導 作業事故・災害の防止対策など | 衛生診断・指導 作業環境改善策の提案や教育 健康リスクの調査・対策支援 衛生管理体制評価など |
| 専門分野 | 機械・電気・化学・土木・建築で区分 | 保健衛生・労働衛生工学で区分 |
| 目的 | 労働者が安全に作業できる職場環境づくりを支援 | 労働者の健康障害や職業性疾患の未然防止 快適な職場環境の実現を支援 |
労働安全コンサルタントに依頼するメリット
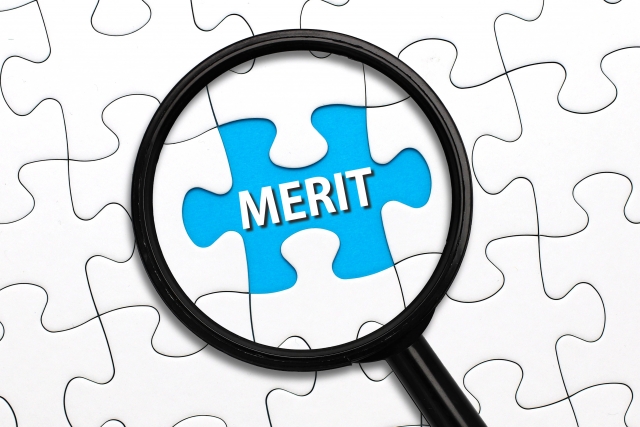
企業が労働安全コンサルタントを活用することで、次のような効果が得られます。
労働災害の防止
労働安全コンサルタントは、現場に潜む危険要因を第三者の視点で洗い出し、具体的な改善策を提案します。
改善策によって事故やトラブルを未然に防ぐことで、人的被害や設備の損傷、業務の中断といった損失を回避できます。
さらに、安全衛生管理体制そのものの見直しを通じて、場当たり的な対応に終わらない継続的な改善活動を支援してもらえる点も大きなメリットです。
法令遵守の徹底
労働安全衛生法をはじめとする関連法令は、改正や解釈の変更が頻繁に発生します。
対応が不十分なままでは、行政指導や罰則、社会的信用の低下といったリスクを招くおそれがあります。
労働安全コンサルタントの支援を受ければ法令の最新動向を踏まえた体制整備が可能になり、現場の実情に即した実効性のある管理が行えます。
労働安全コンサルタントの資格について

労働安全コンサルタントは、厚生労働大臣が認定する国家資格です。
現場の安全に関する高度な知識と実務能力が求められるため、受験には一定の実務経験が必要となります。
受験資格
受験資格は学歴ごとに異なります。
理工系大学を卒業している場合、安全関連の実務経験が5年以上必要です。
高専卒は7年以上、その他の学歴では10年以上の経験が求められます。
また、「1級施工管理技士」や「技術士」など特定国家資格合格者は経験年数不要で受験可能な特例もあります。
対象となる実務は、安全管理、リスクアセスメントの実施などです。
試験内容
■ 筆記試験(1日で実施)
- 産業安全一般(択一式30問/300点、2時間)
- 産業安全関係法令(択一式15問/150点、1時間)
- 専門科目:機械・電気・化学・土木・建築のいずれか1分野(記述式2問/300点、2時間)
- 当該年度4月1日現在の法令等が適用されます。
■ 口述試験
筆記試験合格者のみが対象です。
実務経験や現場での応用力について、面接形式で質疑が行われます。
■出題範囲
- 労働安全衛生法(関連法令)
- 安全管理技術
- 作業環境管理
- 災害防止対策
- 安全教育・指導など
専門分野ごとに機械安全管理、化学安全、土木・建築現場の安全など、その実務内容に即した設問がなされます。
合格基準・合格率
筆記試験は総得点の60%以上、かつ各科目で40%以上の得点が必要です。
合格率は毎年10〜15%前後とされ、比較的難易度の高い資格となっています。
試験日程
筆記試験は毎年10〜11月に全国主要都市で実施され、結果発表後に口述試験が行われます。
最終的な合格発表は年明けです。
まとめ
労働安全コンサルタントは、労働現場における安全管理の専門家です。
企業が安全対策の改善を図る際に依頼することで、職場環境の向上と安全水準の強化を実現できます。
自社の安全対策に課題を感じている場合は、労働安全コンサルタントへの相談を検討してみてはいかがでしょうか。

株式会社G-place 設備資材事業グループ
📞03-3527-2992
受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
■関連ニュース記事
2024/12/10 労働新聞社
【お役立ち資料箱】高所作業のリスク再検討を 安全措置が不十分で死亡災害も 長野・松本労基署
2024/09/10 労働新聞社
適正業者登録制創設へ 安全管理の取組みを評価 墜転落災害防止で 仮設工業会
2024/08/09 労働新聞社
【トピックス】高所作業の墜落対策を確認 重点業種で好事例水平展開へ 労働局がパトロール 全国安全週間
2024/08/09 労働新聞社
足場業者に登録制度 労災減少めざし創設へ 仮設工業会
2024/06/21 RSK山陽放送
建設現場ではどんな安全対策を?労災事故が多くなるといわれる夏を前に岡山労働局が岡山市役所・新庁舎の建設現場を視察
2024/04/08 株式会社 流通研究社
厚労省、墜落制止用器具の規格不適合製品を公表
2024/01/29 日本経済新聞
西尾レント、転落防止フック未装着を検知 建設現場向け
2023/12/05 ハーバード・ビジネス・レビュー
労働者を危険から守りたければ、自社だけで安全対策してはいけない

