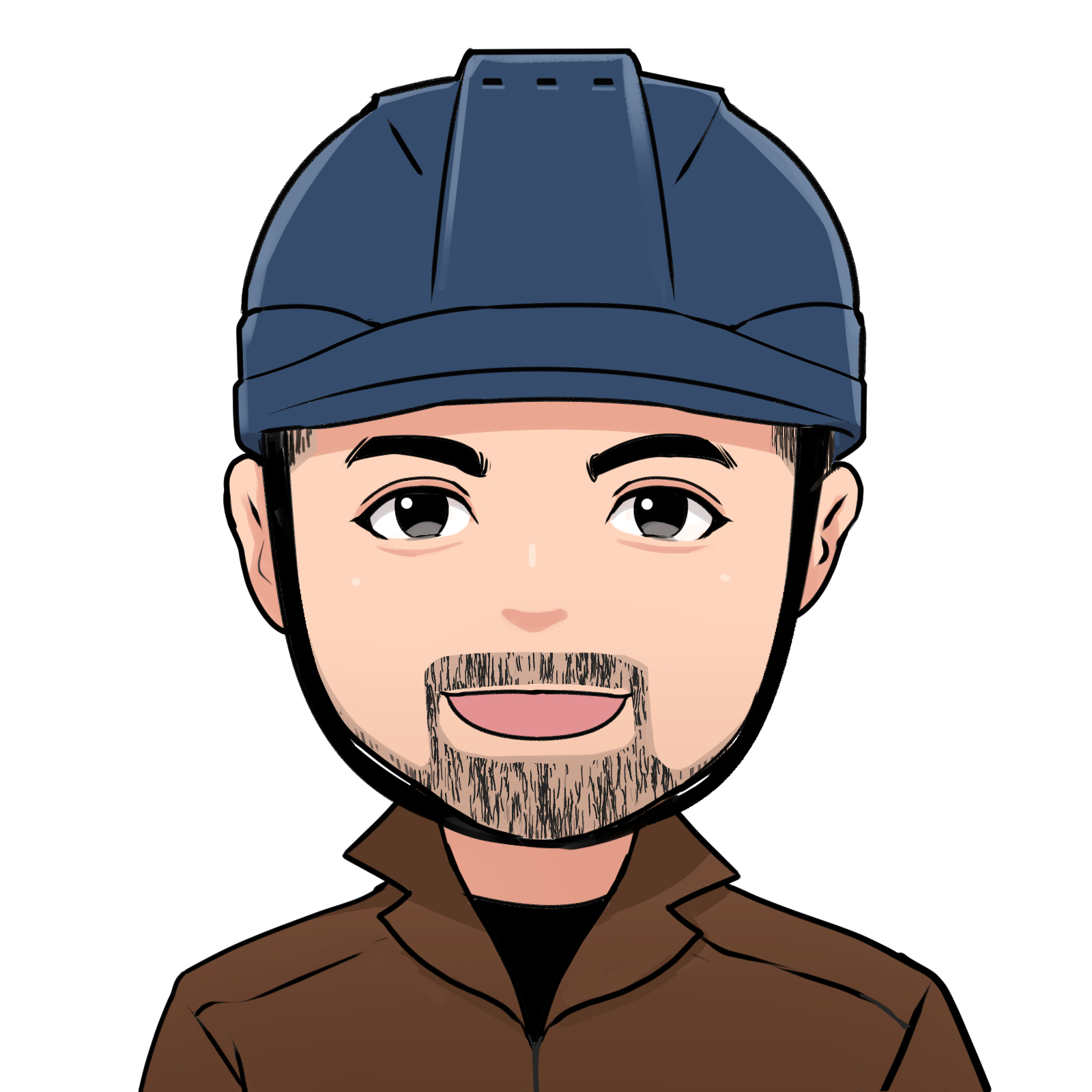
高所作業時の事故を「ゼロ」に!
株式会社G-Place 設備資材事業グループの平野です。
弊社では現場での高所事故を防ぐべく、年間のべ50件以上の現場にお邪魔し高所安全対策のご提案をしています。
このコラムでは「リスクアセスメント」に視点を向けて、安全対策を考えてみたいと思います。
ぜひご参考にしていただければと思います。
日々現場で働くみなさんは、リスクアセスメントについてどのくらい理解していますか。
職場の安全管理において、リスクアセスメントは欠かせない取り組みです。
これが不十分だと労働災害につながる恐れがあります。
この記事では、リスクアセスメントの基本的な考え方から実施手順、事例までを解説し、現場で活かせる知識をお伝えします。
リスクアセスメントとは

リスクアセスメントは、職場に潜む危険源(ハザード)を洗い出し、それらが引き起こすリスクを評価して、効果的な対策を検討・実施するための一連のプロセスです。
労働安全衛生法では、事業者に対してリスクアセスメントの実施を努力義務としています。
また、事業主だけでなく労働者も参加することが求められており、労働者には災害が起こり得る状況を把握・指摘するとともに、防止策を遵守する責任が課せられています。
リスクアセスメントで得られる効果

リスクアセスメントを実施することで得られる効果は以下の通りです。
労働災害が未然に防げる
リスクアセスメントは、事故を未然に防ぐことに主眼を置いた予防的なアプローチです。
潜在的な危険を早い段階で洗い出し、対策を講じることによって事故や健康障害を防げます。
安全意識の高まり
従業員が作業に潜む危険を認識することで、安全に対する意識が高まります。
リスクアセスメントは現場の作業員や監督者の参加を得て実施するため、職場全体でリスクに対する共通認識を持つことができます。
従業員がリスクアセスメントへ積極的に参加すれば、主体性を持って安全教育を受けられ、職場全員の安全意識向上が見込めます。
安全衛生対策の優先順位がわかる
リスクを見積もることで、実施する安全衛生対策の優先順位が客観的指標に基づいて決定できます。
従業員は「なぜ注意して作業しなければならないか」を合理的に理解でき、適切に優先順位をつけて安全対策ができます。
企業価値の向上
リスクアセスメントへの取り組みは、従業員が安心・安全な職場環境で作業できる試みであることはもちろん、取引先からの信用性・評価にも関わります。
普段からリスクアセスメントを徹底していれば、自社の信用性向上も見込めます。
リスクアセスメントの方法
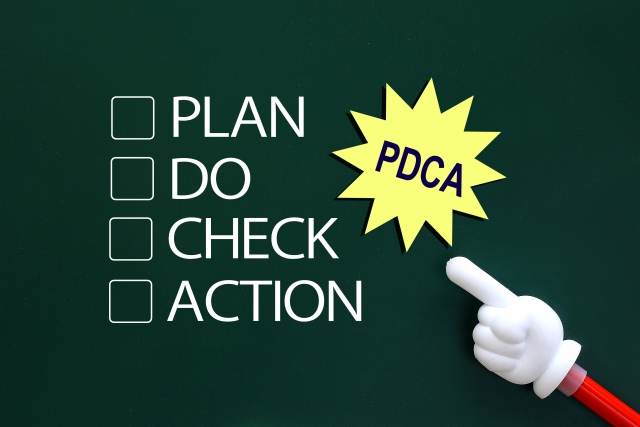
リスクアセスメントは、以下の6つのステップで実施します。
各ステップを確実に実行することで、効果的なリスク管理が可能になります。
①危険性や有害性の特定
最初のステップは、何がどのように危険かを洗い出すこと。
具体的には職場に存在するすべての危険源(ハザード)を漏れなく特定することです。
この段階では、以下の手法を組み合わせて実施します。
- 作業工程の分析:各作業工程を細かく分解し、それぞれの段階で発生しうる危険を洗い出します
- 過去の事故事例の分析:自社および他社の事故事例から、類似の危険を特定します
- ヒヤリハット情報の活用:日常的に収集しているヒヤリハット報告から危険源を抽出します
- 現場巡視:実際に作業現場を観察し、潜在的な危険を発見します
- 従業員へのヒアリング:現場作業者から直接、危険と感じる箇所を聞き取ります
- 回転する機械部品への巻き込まれ
- 高所作業での転落
- 重量物運搬時の腰痛
- 化学物質による健康障害
- 騒音による聴力障害
②リスクの見積もり
次のステップは、リスクの見積もりです。
ここでは特定した危険源について「発生の可能性」と「被害の重大性」の2つの観点から評価します。
マトリクス法によって発生頻度と被害の大きさを段階的に評価し、リスクレベルを算出します。
| 評価項目 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 |
|---|---|---|---|---|
| 発生の可能性 | ほとんどない (年1回未満) | 可能性がある (年数回) | 比較的高い (月1回程度) | 高い (週1回以上) |
| 被害の重大性 | 軽微 (応急処置程度) | 中程度 (休業1週間未満) | 重大 (休業1ヶ月以上) | 致命的 (死亡・重篤な後遺症) |
リスクレベルは、「発生の可能性」×「被害の重大性」で算出し、数値が高いほど優先的に対策を講じる必要があります。
③リスクの優先順位付け
算出したリスクレベルに基づいて、対策の優先順位を明確化します。
一般的な優先順位の基準は以下の通りです。
| リスクレベル | 対応区分 | 必要な対策 |
|---|---|---|
| 12〜20 | 許容不可能 | 直ちに作業中止、即座に改善措置を実施 |
| 9〜11 | 重大 | 速やかに改善措置を実施(1ヶ月以内) |
| 6〜8 | 中程度 | 計画的に改善措置を実施(3ヶ月以内) |
| 5以下 | 許容可能 | 必要に応じて改善、定期的な監視を継続 |
④リスク低減のための対策の検討
リスク低減対策は「リスク低減の優先順位」に基づいて検討します。
まず工学的対策で危険源そのものを取り除くことを最優先とし、それが困難な場合に管理的対策を講じ、最後の手段として個人用保護具によって補完するという考え方です。
リスク低減対策は、以下の優先順位に基づいて検討します。
工学的対策(リスクの隔離)
危険源そのものを除去・代替、または作業者から隔離する。
安全装置の設置なども含みます。
管理的対策(リスクの回避)
作業手順の整備、標準化、安全教育、立入制限、作業許可制度の導入など。
個人用保護具(リスクの低減)
ヘルメット、安全靴、保護眼鏡、呼吸用保護具、耐切創手袋などを着用させる。
⑤対策の実施
決定した対策を確実に実施するために、実施計画を立案し、PDCAサイクルで管理します。
- 実施責任者の明確化:各対策に責任者を割り当て、権限と責任を明確にします
- 実施期限の設定:リスクレベルに応じた適切な期限を設定します
- 必要な資源の確保:予算、人員、設備などを事前に準備します
- 関係者への周知:対策内容を全従業員に周知し、協力体制を構築します
- 実施状況の監視:定期的な進捗確認と必要に応じた計画の見直しを行います
⑥効果測定
対策実施後は、定量的・定性的な指標を用いて効果を測定し、継続的な改善につなげます。
定量的指標
- 労働災害発生件数の推移
- ヒヤリハット報告件数の変化
- 安全パトロールでの指摘事項数
- リスクレベルの改善度
定性的指標
- 従業員の安全意識調査結果
- 作業のしやすさに関するフィードバック
- 安全活動への参加率
さらに、対策によって新たなリスクが生じていないかも確認します。
効果測定の結果は文書化し、次回のリスクアセスメントに活かすことが重要です。
リスクアセスメントの実践事例

実際の現場でリスクアセスメントがどのように活用されているか、業界別の具体的な事例を紹介します。
製造業での事例:プレス作業の安全対策
課題
金属プレス作業において、年間数件の挟まれ事故が発生
リスクアセスメント結果
- リスクレベル:16(発生可能性4×重大性4)
- 主な危険源:両手操作式安全装置の不備、作業手順の不徹底
対策
- 光線式安全装置の導入(工学的対策)
- インターロック機能付き安全ガードの設置(工学的対策)
- 作業手順書の改訂と定期教育の実施(管理的対策)
考えられる結果:導入後2年間、挟まれ事故ゼロを達成。ヒヤリハット報告も80%減少
建設業での事例:高所作業の転落防止
課題
高層ビル建設現場で転落リスクが常に存在
リスクアセスメント結果
- リスクレベル:12(発生可能性3×重大性4)
- 主な危険源:安全帯の不適切な使用
対策
- 先行手すりの全面設置
- 安全ネットの多層配置
- フルハーネス型安全帯の導入と使用訓練
- 毎日の作業前KY(危険予知)活動の徹底
考えられる結果:転落事故ゼロを3年間継続。全国安全週間で表彰を受賞
化学工場での事例:有害物質のばく露防止
課題
有機溶剤を使用する作業で健康障害のリスク
リスクアセスメント結果
- リスクレベル:9(発生可能性3×重大性3)
- 主な危険源:局所排気装置の能力不足、保護具の不適切な選定
対策
- プッシュプル型換気装置への更新
- 作業環境測定の頻度を月1回に増加
- 化学物質リスクアセスメント(コントロールバンディング)の導入
- 適切な呼吸用保護具の選定と fit test の実施
考えられる結果:特殊健康診断での有所見率が50%減少
リスクアセスメントの課題・対策

リスクアセスメントは効果的な手法ですが、実際の運用においては様々な課題に直面することがあります。
対策と共に紹介します。
情報不足
危険源の特定やリスク評価に必要な情報が不十分だと、精度や信頼性に影響します。
対策
- 経営層の積極的な関与と安全への投資
- 現場作業者の意見を重視した実践的な評価
- 定期的な見直しと更新の仕組み化
- 成功事例の共有と水平展開
経営層の支援による体制強化と現場の声の反映を両立させることが重要です。
また、古い評価基準に頼らず、定期的に更新しながら他社事例も活用することで精度と実効性を高められます。
リスク評価のばらつき
評価者の経験や感受性の違いによって、同じリスクでも評価結果が変わることがあります。
対策
- 第三者による評価の実施
- 他部署からの参加者を含めた評価チームの編成
- 過去の災害事例データベースの活用
- 定期的な評価基準の見直し
リスク評価はどうしても主観に左右されがちです。
そのため、第三者や他部署のメンバーを交えた多角的な視点が有効です。
評価基準を定期的に見直す仕組みを組み込むことで、ばらつきを減らし精度を高められます。
新たなリスクの見落とし
技術革新や設備更新に伴い、従来にないリスクが発生することがあります。
対策
- 新規設備導入時の事前評価の徹底
- 変更管理の導入
- 非定常作業のリスクアセスメント強化
- 協力会社作業も含めた包括的な評価
新しい設備や作業方法の導入は効率や品質を高める一方で、予期せぬ危険を伴うことがあります。
こうしたリスクを防ぐには、導入段階での評価や変更管理の仕組みを整えることが不可欠です。
また、普段は行わない非定常作業や協力会社の作業も含めて包括的に評価することで、見落としを防ぎ、事故を未然に防止できます。
リソースの制約
中小企業では、リスクアセスメントに割ける時間や人員が限られています。
対策
- 簡易版リスクアセスメント手法の活用
- 業界団体が提供するツールやテンプレートの利用
- 外部専門家によるサポートの活用
- 段階的な導入
限られたリソースの中で効率的にリスクアセスメントを進めるには、負担を軽減できる仕組みを取り入れることが大切です。
簡易版や業界団体のツールを活用すれば短時間で評価を行え、外部の専門家を活用することで社内の不足を補えます。
最初から全工程を対象にせず、重要な工程から段階的に展開していくことで現実的に取り組めます。
従業員の理解
全従業員がリスクアセスメントの重要性を理解し、積極的に参加することが不可欠です。
対策
- 分かりやすい教育資料の作成
- 実際の事故事例を用いた勉強会
- サークル活動での取り組み
- 改善提案制度との連携
従業員が「自分ごと」として捉えなければ、リスクアセスメントは形骸化してしまいます。
視覚的に理解しやすい教育資料や、現場で起きた実際の事故事例を取り上げた座学は効果的です。
さらに、QCサークルなど活動を取り入れたり、改善提案制度と連携させることで日常業務の中にリスクアセスメントが浸透していきます。
継続的な改善の仕組み
リスクアセスメントは一度実施して終わりではなく、PDCAサイクルを回し続けることが重要です。
対策
- 年間計画の策定と進捗管理
- KPI(重要業績評価指標)の設定と監視
- 内部監査によるチェック機能
- マネジメントレビューでの評価
リスクアセスメントを継続的に改善していくには、仕組みとして定着させることが重要です。
年間計画やKPIを設定すれば進捗を数値で把握でき、内部監査によって運用状況を確認できます。
マネジメントレビューで経営層が定期的に評価することで、組織全体として安全活動を強化し、改善のサイクルを確実に回せるようになります。
まとめ
リスクアセスメントは、労働災害を未然に防ぎ、安全で健康的な職場環境を実現するための基本的な手法です。
本記事では、その考え方から実践の流れ、現場での事例までを紹介しました。
リスクアセスメントを定着させるために重要なのは、職場全体で主体的に取り組む活動とすることです。
災害件数の減少や作業効率の向上、コスト削減といった成果を数値で示して「見える化」し、従業員にフィードバックすることで、安全への意識と参加意欲が高められます。
リスクアセスメントを継続して実践し、より安全で安心できる職場づくりを進めていきましょう。

株式会社G-place 設備資材事業グループ
📞03-3527-2992
受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
■関連ニュース記事
2024/12/10 労働新聞社
【お役立ち資料箱】高所作業のリスク再検討を 安全措置が不十分で死亡災害も 長野・松本労基署
2024/09/10 労働新聞社
適正業者登録制創設へ 安全管理の取組みを評価 墜転落災害防止で 仮設工業会
2024/08/09 労働新聞社
【トピックス】高所作業の墜落対策を確認 重点業種で好事例水平展開へ 労働局がパトロール 全国安全週間
2024/08/09 労働新聞社
足場業者に登録制度 労災減少めざし創設へ 仮設工業会
2024/06/21 RSK山陽放送
建設現場ではどんな安全対策を?労災事故が多くなるといわれる夏を前に岡山労働局が岡山市役所・新庁舎の建設現場を視察
2024/04/08 株式会社 流通研究社
厚労省、墜落制止用器具の規格不適合製品を公表
2024/01/29 日本経済新聞
西尾レント、転落防止フック未装着を検知 建設現場向け
2023/12/05 ハーバード・ビジネス・レビュー
労働者を危険から守りたければ、自社だけで安全対策してはいけない

