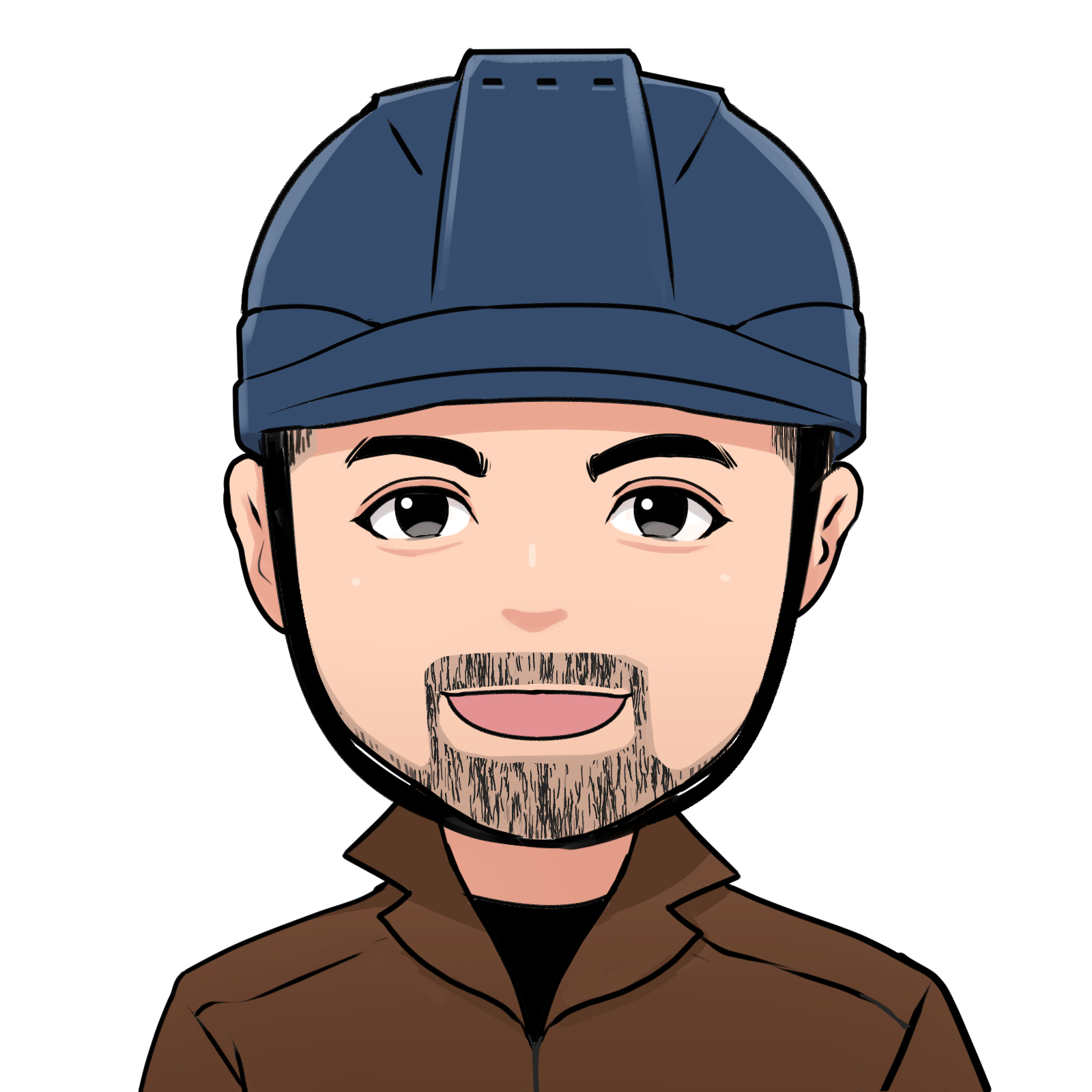
高所作業時の事故を「ゼロ」に!
株式会社G-Place 設備資材事業グループの平野です。
弊社では現場での高所事故を防ぐべく、年間のべ50件以上の現場にお邪魔し高所安全対策のご提案をしています。
このコラムでは「外壁打診診断」に視点を向けて、安全対策を考えてみたいと思います。
ぜひご参考にしていただければと思います。
高層ビルやマンションの外壁で作業している人を見かけたことがあるかもしれません。
代表的なのは清掃作業ですが、それ以外にも「外壁打診調査」と呼ばれる重要な点検作業が行われている場合があります。
外壁打診調査は、建物の安全性を確保するために欠かせない作業です。
本記事では、外壁打診調査の目的や内容、実施方法や安全対策についてわかりやすく解説します。
外壁打診調査とは

外壁打診調査は、建物の外壁に浮きや剥離といった異常がないかを確認するための点検方法です。
タイルやモルタルなどの仕上げ材が構造躯体から部分的に浮いている場合、見た目では異常がわからないことが多いので打診棒という専用の器具を使って壁を打診し、音の違いで内部の状態を判断します。
外壁打診調査の目的は、外壁の落下事故を未然に防ぐために行われます。
外壁がもろくなった状態を放置すると剥がれ落ちた際に歩行者に当たり、重大事故につながるおそれがあります。
調査の対象となる外壁は、以下のようなものが中心です。
- タイル貼り仕上げ(磁器質タイル、せっ器質タイルなど)
- モルタル系の吹き付け仕上げ
- 外装パネルや石貼りなどの乾式工法仕上げ
外壁打診調査の方法

外壁打診調査では、調査対象となる外壁面にどうやって安全かつ確実に近づくかが課題となります。
建物の高さや立地条件、調査範囲によって最適な方法は異なります。
ここでは外壁打診調査を行うときの代表的な3つの調査方法を紹介します。
足場を設置して調査する方法
最も一般的で精度が高い方法が、足場を設置して行う打診調査です。
作業員が安定した作業床上で外壁に接近できるため、打音や目視が確実に行えるというメリットがあります。
ただし、足場の設置・解体には時間と費用がかかること、また建物の周囲にスペースが必要となるため、狭かったり交通量の多い場所では対応が難しいことがあります。
高所作業車を使う方法
高所作業車による方法は、足場を組まずに短期間で調査を行えるため、中低層の建物や部分的な調査に適しています。
ただし、車両の安定配置や地盤条件に制約があるため、事前に敷地内の進入経路や作業スペースを確認しておく必要があります。
また、物理的に届かない高さの建物の場合は使えません。
ロープアクセスによる調査方法
仮設足場や高所作業車が設置できない場合、ロープアクセスによる打診調査が選択されることもあります。
建物の上部からロープで吊り下がり、作業員が下降しながら外壁面を調査します。

打診調査の流れ

外壁打診調査は、単に壁を叩くだけの単純な作業ではありません。
調査前の準備から調査中の記録、調査後の報告書作成まで、一連の工程を計画的に進める必要があります。
ここでは、現場での基本的な流れを4つのステップに分けて紹介します。
調査対象と範囲の設定
まず、建物全体の中でどの部位を対象とするかを決定します。
定期報告に対応する調査であれば、全面を対象にするのが原則です。
部分補修に向けた調査であれば、劣化の疑いがある面や過去に補修歴のある場所を重点的に設定します。
調査範囲を明確にするためには、設計図や立面図を確認しながら打診面積・使用機材・必要人員などを見積もっておくことが重要です。
打診棒を使った打音の確認
調査の本体となる作業が、仕上げ材に打診棒を当てて音を確認する工程です。
外壁に浮きや剥離があると、打音が鈍く濁ったように響きます。
健全部と比較しながら音の変化を聞き分け、異常箇所を識別していきます。
マーキング
もし異常が確認されたら、チョークやマーキングテープなどで位置を明示します。
マーキングした位置は、立面図や図面上にも正確に反映させます。
使用する記録媒体は紙図面・タブレット・写真など現場に応じて使い分けます。
報告書の作成
調査完了後は、図面や写真、記録シートなどをもとに調査結果を整理し、報告書を作成します。
報告書には、異常箇所の位置と数量、異常の種類(浮き・剥離など)、推定原因、補修の必要性などを明記します。
建築基準法に基づく定期報告の場合は、所定の書式と様式に従い、所管行政庁へ提出します。
修繕計画に組み込む場合には、補修方法や工事の優先順位に関する所見も含めるのが一般的です。
外壁打診調査の安全対策

外壁打診調査は、建物の高所で行われる作業が中心になります。
足場の上や高所作業車のバスケット、あるいはロープで吊り下がるような環境では、わずかなミスが重大事故につながることもあります。
ここでは、調査の現場で求められる基本的な安全対策についてお伝えします。
高所での墜落防止措置
作業員が立ち入る可能性のある場所には、必ず墜落防止措置が求められます。
足場を使用する場合は、手すりや落下防止ネットの設置が基本となり、作業中も親綱やライフラインへのフック接続が義務付けられます。
ロープアクセス調査では、フルハーネス型の墜落制止用器具を使用し、主ロープと補助ロープをそれぞれ独立して管理します。
現場の構造に合わせたシステム設計と、事前の安全計画の策定が不可欠です。
使用する器具の選定
墜落制止用器具、ロープ、カラビナ、アンカーなど、安全確保に関わる器具はすべて適切な規格に適合したものを使用する必要があります。
使用状況に応じた選定を行わなければ、器具が本来の性能を発揮できず、安全性が著しく損なわれます。
また、ハーネスの装着方法やバックルの締め方に誤りがあると、墜落時の衝撃が身体に集中し、大きな障害を招くおそれもあります。
まとめ
外壁打診調査は、建物の安全性を維持する上で欠かせない点検作業です。
外壁の浮きや剥離は、見た目では判断できない場合が多く、落下事故を未然に防ぐためには、定期的かつ丁寧な調査が求められます。
調査には、足場・高所作業車・ロープアクセスなど、現場の条件に応じた方法を選ぶ必要があります。
どの方法を選ぶ場合でも、作業員が安全に調査を進められる環境を整えることが前提です。
打診の精度を高めることと、安全対策を徹底することは切り離せません。

株式会社G-place 設備資材事業グループ
📞03-3527-2992
受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
■関連ニュース記事
2024/12/10 労働新聞社
【お役立ち資料箱】高所作業のリスク再検討を 安全措置が不十分で死亡災害も 長野・松本労基署
2024/09/10 労働新聞社
適正業者登録制創設へ 安全管理の取組みを評価 墜転落災害防止で 仮設工業会
2024/08/09 労働新聞社
【トピックス】高所作業の墜落対策を確認 重点業種で好事例水平展開へ 労働局がパトロール 全国安全週間
2024/08/09 労働新聞社
足場業者に登録制度 労災減少めざし創設へ 仮設工業会
2024/06/21 RSK山陽放送
建設現場ではどんな安全対策を?労災事故が多くなるといわれる夏を前に岡山労働局が岡山市役所・新庁舎の建設現場を視察
2024/04/08 株式会社 流通研究社
厚労省、墜落制止用器具の規格不適合製品を公表
2024/01/29 日本経済新聞
西尾レント、転落防止フック未装着を検知 建設現場向け
2023/12/05 ハーバード・ビジネス・レビュー
労働者を危険から守りたければ、自社だけで安全対策してはいけない


