
高所作業時の事故を「ゼロ」に!
株式会社G-Place 設備資材事業グループの平野です。
弊社では現場での高所事故を防ぐべく、年間のべ50件以上の現場にお邪魔し安全対策のご提案をしています。
このコラムでは「ハインリッヒの法則」をご紹介します!
聞いたことがある方もない方も、安全衛生の豆知識として、ぜひご参考にしていただければと思います。
突然ですが、「ハインリッヒの法則」とはどのような法則なのかご存知でしょうか?
ハインリッヒの法則は、職場の安全衛生管理において重要な考え方として広く知られています。
「よく知っているよ!」
「名前は聞いたことがあるかも」
「名前も来たことないし、なんじゃそれ?」
いろんな反応があるかと思います😊
そこで、このコラムではハインリッヒの法則についてわかりやすく解説します。
職場の安全衛生にかかわる他の理論についても紹介するので、誰もが安心・安全に働ける環境づくりの一助にご活用ください!
ハインリッヒの法則とは?

ハインリッヒの法則は、20世紀前半にアメリカの損害保険会社で統計分析の専門家として働いていたハーバート・ウィリアム・ハインリッヒが提唱した法則です。
ハインリッヒは、工場で発生した事故や労働災害を統計分析し、一定の法則性があることを導き出しました。
その研究結果は、1931年に自身の著書『Industrial Accident Prevention: A Scientific Approach』にまとめられています。
日本では1951年に『災害防止の科学的研究』として邦訳され、労働安全の分野で広く知られるようになりました。
この法則は「1:29:300の法則」や「ヒヤリハットの法則」とも呼ばれています。
1件の重大事故の背景には、29件の軽微な事故があり、さらにその裏には300件のニアミス(ヒヤリ・ハット)があるとされています。
300件ヒヤリハットがあれば1件が重大事故につながる!
- 300件の270件は運よく事故に繋がらなかった
- 300件中29件が軽微な事故に繋がる
- 300件中1件が重大事故が発生してしまう
労働災害の発生頻度を見積もる指標として活用されており、事故や災害の防止に関する基本的な考え方として世界的に定着しています。
例えばこんなヒヤリハット

厚生労働省の職場のあんぜんサイトで、高所作業のヒヤリハット事例について紹介されていますので抜粋してお伝えしていきます。
- トラックの荷台での作業中テールゲートリフターから転落しそうになった
- 選定作業中の安全帯を付け替えた時に枝が折れて墜落しそうになった
- 脚立を用いての作業中に足が滑り落ちそうになった
- 脚立のロックを忘れていてぐらつき落ちそうになった
- 高所でのボルト穴調整の作業中にシノが外れた反動で転落しそうになった
- 家屋の屋根での作業中に梁の通っていない箇所を歩いてしまった
- クレーン作業中の作業者に荷物が当たりそうになった
- スマホを見ながら歩いていて階段を踏み外してしまった
ここでお伝えしたヒヤリハットは一例ですが、まだまだ職場によってさまざまなヒヤリハットがあります。
日々の作業中に、一度は「ヒヤリ」とした経験があるという方も多いのではないでしょうか?
結果的に重大事故に繋がらなくてよかったものの、それを何度も繰り返していてはいつか大きな事故に繋がる恐れがあるのです。
職場の安全衛生とハインリッヒの法則

職場の安全衛生を考える上で、ハインリッヒの法則はどのように活用したら良いのでしょうか。
ここでは、事故・災害を防止するという視点でハインリッヒの法則の活用方法を紹介します。
ニアミスの発生頻度を減らすことの重要性
ハインリッヒの法則は、工場で発生した事故や労働災害を統計的に分析し、一定の法則性を導き出したものです。
危険を伴う作業を行う現場では、300回のニアミスのうち1回は重大な事故につながる可能性があるとされています。
ニアミスの段階では実際の被害が発生していないため、大きな問題とは認識されにくいかもしれません。
しかし、ハインリッヒの法則に従えば、ニアミスが多い環境ではいずれ軽微な事故が発生し、さらに重大な事故につながるリスクが高まります。
そのため、職場の安全衛生管理において、まずはニアミスの発生を減らすことが欠かせません。
ヒヤリハットの収集・共有で事故を未然に防ぐのが大切
繰り返しになりますが、職場の安全衛生を考えるときに重要なのが、ニアミスをいかにして減らすかです。
ただし、発生するニアミスの種類は、現場ごとに異なります。
そのため、現場で働く従業員からヒヤリハットの情報を収集し、共有する機会を設けることが効果的です。
どのような場面でヒヤリハットが発生しやすいかを認識することで、ニアミスの発生頻度を抑えられます。
職場で安全衛生委員会を設置する際は、ヒヤリハットの収集と共有を積極的に行うことが大切です。
危険を伴う作業だけでなくオフィスワークでも重要
ハインリッヒの法則は、工場など危険を伴う作業に着目して導き出されたものですが、オフィスワークなどの職場環境でも無関係ではありません。
例えば、ロッカーの上に書類を積み上げていると、扉の開閉時に落下して怪我をするリスクがあります。
電源タップにほこりが溜まると、漏電による火災が発生する可能性もあります。
また、出会い頭の衝突や濡れた床で滑って転倒など、身近なところに危険は潜んでいます。
オフィスワークでもヒヤリハットの情報を収集し、安心して働ける環境づくりが大切です。
ハインリッヒの法則に関連する2つの法則
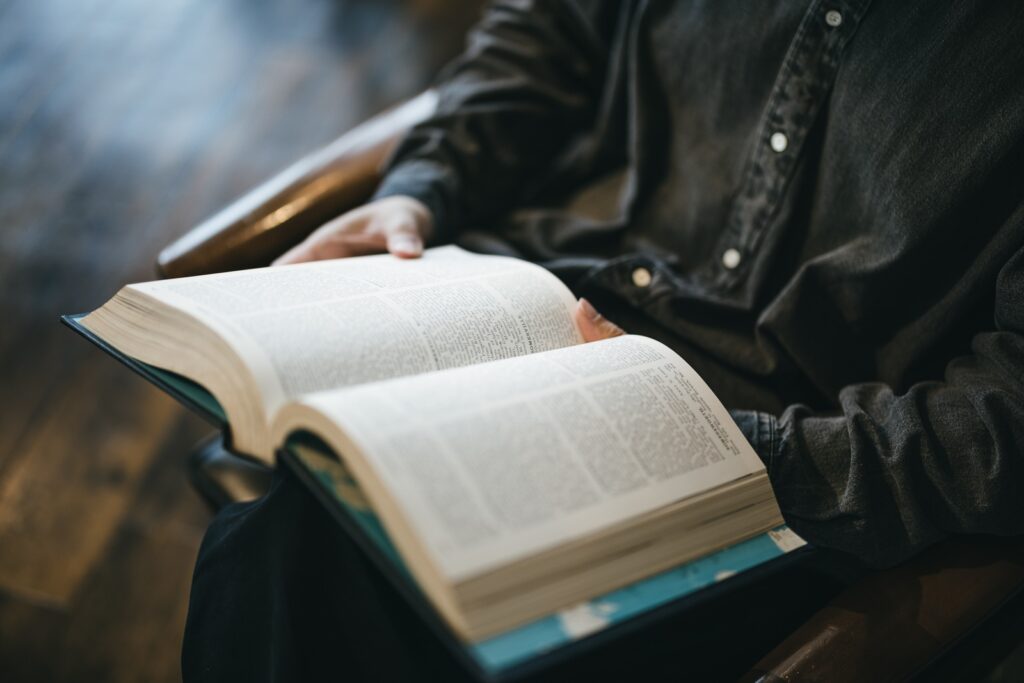
ハインリッヒの法則と同様に事故や災害のリスクについての統計に基づく法則や、関連する理論はたくさんあります。
その中でも有名な2つの法則をご紹介いたしますのでこちらも参考にしてください。
バードの法則
バードの法則は、アメリカのフランク・バードが1969年に統計分析をもとに導き出した法則です。
この法則では、重傷災害、軽傷災害、物損事故、ニアミスの発生比率が1:10:30:600であるとされています。
ニアミス > 物損事故 > 軽傷災害 > 重症災害
(600) (30) (10) (1)
タイ・ピアソンの法則
タイ・ピアソンの法則は、イギリスのタイとピアソンが1974年から1975年にかけて収集したデータを統計分析し、導き出した法則です。
この法則では、重傷災害、軽傷災害、応急処置、物損事故、ニアミスの発生比率が1:3:50:80:400であるとされています。
ニアミス > 物損事故 > 応急処置 > 軽傷災害 > 重症災害
(400) (80) (50) (3) (1)
3つの法則からわかること
バードの法則やタイ・ピアソンの法則は、ハインリッヒの法則よりも細分化された統計分析に基づいています。
重傷災害と軽傷災害、または軽傷災害と応急処置の境界は明確ではないため厳密に比較することは難しいですが、3つの法則から共通して読み取れるのは、約300~600回のニアミスのうち1回は重大な事故につながるという点です。
どの法則も、ヒヤリハットを減らし、ニアミスの発生を防ぐことが事故防止につながることを示しています。
まとめ
ハインリッヒの法則は、アメリカのハインリッヒが統計分析をもとに導き出した事故や労働災害の頻度に関する法則です。
1件の重大事故を防ぐためには、ニアミスを減らすことがどれほど重要かを数字で示しています。
ハインリッヒの法則によると、約300回のニアミスのうち1回は重大な事故につながるリスクがあるとされています。
職場の安全衛生を維持するには、ニアミスやケアレスミスと呼ばれる「小さなミス」を減らすことが欠かせません。
従業員からヒヤリハットの事例を収集・共有し、軽微な事故すら発生しない、安全な職場づくりを目指しましょう。
G-Placeでは、「高所作業時の事故ゼロ!」をスローガンに、作業現場の安全対策についてご相談を受け付けています。
気になることや不安がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

株式会社G-place 設備資材事業グループ
📞03-3527-2992
受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
■関連ニュース記事
2024/12/10 労働新聞社
【お役立ち資料箱】高所作業のリスク再検討を 安全措置が不十分で死亡災害も 長野・松本労基署
2024/09/10 労働新聞社
適正業者登録制創設へ 安全管理の取組みを評価 墜転落災害防止で 仮設工業会
2024/08/09 労働新聞社
【トピックス】高所作業の墜落対策を確認 重点業種で好事例水平展開へ 労働局がパトロール 全国安全週間
2024/08/09 労働新聞社
足場業者に登録制度 労災減少めざし創設へ 仮設工業会
2024/06/21 RSK山陽放送
建設現場ではどんな安全対策を?労災事故が多くなるといわれる夏を前に岡山労働局が岡山市役所・新庁舎の建設現場を視察
2024/04/08 株式会社 流通研究社
厚労省、墜落制止用器具の規格不適合製品を公表
2024/01/29 日本経済新聞
西尾レント、転落防止フック未装着を検知 建設現場向け
2023/12/05 ハーバード・ビジネス・レビュー
労働者を危険から守りたければ、自社だけで安全対策してはいけない


