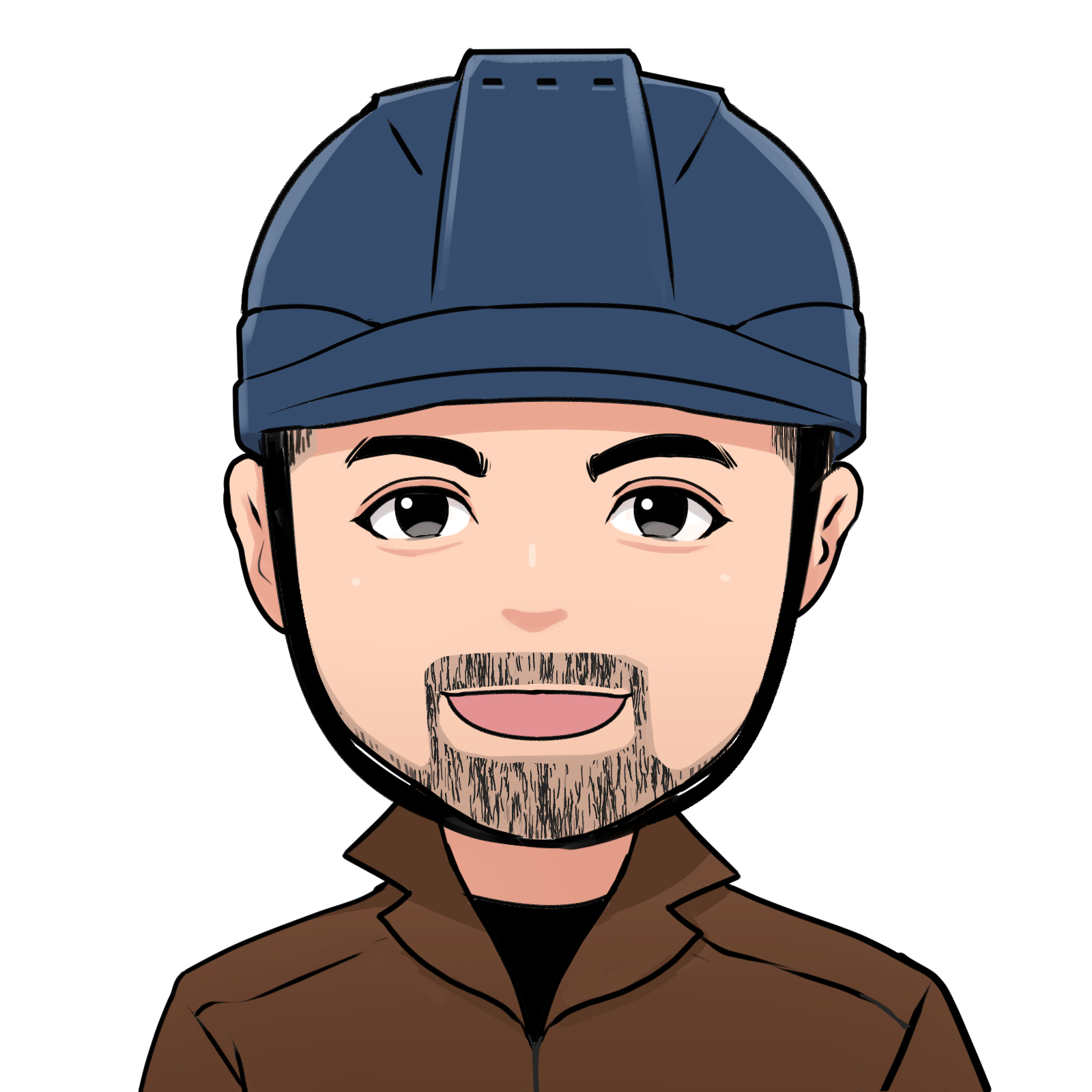
高所作業時の事故を「ゼロ」に!
株式会社G-Place 設備資材事業グループの平野です。
弊社では現場での高所事故を防ぐべく、年間のべ50件以上の現場にお邪魔し高所安全対策のご提案をしています。
このコラムでは「労災事故の推移」に視点を向けて、安全対策を考えてみたいと思います。
ぜひご参考にしていただければと思います。
労災事故は、毎年多くの現場で発生しています。
安全意識の向上や制度整備が進んでいますが、実際に事故件数はどう推移しているのでしょうか。
この記事では、労災事故の発生件数や死亡災害の年次推移をもとに業種別の傾向や増減の要因、安全対策の動向をお伝えします。
統計から見えてくる日本の労働現場の課題と、今後求められる取り組みにも注目していきます。
労災事故の定義

労災事故とは、労働者が業務中または通勤中の事故が原因で負傷したり、後遺障害が残ったり、死亡することです。
労災事故が発生した場合、会社は「労働者死傷病報告」を労働基準監督署に提出する義務があります。
このデータを厚生労働省が集計し、労働災害発生状況として公表・管理しています。
統計は、以下の2つに分けて集計されています。
- 業務災害:工場や建設現場などでの作業中に発生した事故
- 通勤災害:通勤途中に交通事故などで負傷・死亡したケース
厚生労働省の公表する「労働災害発生状況等調査」では、死亡者数、休業4日以上の死傷者数、災害の種類別、業種別など、さまざまな角度から集計が行われています。
なお、1日だけの休業や軽微なけがは、統計に含まれないケースが多いため、実際のヒヤリハットや軽傷例は、数字以上に存在していると考えられます。

全体件数の推移
労災事故の発生件数は、時代の変化や制度の見直しに伴って推移してきました。
厚生労働省が発表している統計によれば、昭和の高度経済成長期には労災件数が非常に多く、年間で数千人規模の死亡災害が発生していた時期もあります。
近年の推移を見ると、死亡災害については長期的には減少傾向が続いています。
| 年度 | 死亡者数(人) | 休業4日以上の死傷者数(人) |
|---|---|---|
| 1960年(昭和35年) | 6,000~6,500人 | 125,918人 |
| 1980年(昭和55年) | 3,009人 | 335,706人 |
| 2000年(平成12年) | 1,889人 | 133,948人 |
| 2010年(平成22年) | 1,195人 | 107,759人 |
| 2020年(令和2年) | 784人 | 125,115人 |
昭和には年間数千人を超えていた死亡者数が、令和に入ってからは年間800人前後まで減少しています。
一方で、休業4日以上の死傷災害件数は、減少傾向が一時停滞し、近年ではやや増加に転じていることもわかります。
死亡災害が減っている一方で、日常的な労災リスクへの対応が求められる局面に差し掛かっているといえるでしょう。
増減の要因

労災事故の件数が増減する背景には、さまざまな社会的・構造的要因があります。
ここでは代表的な要因をお伝えします。
高齢化の影響
日本は世界でも類を見ない超高齢社会です。
現場で働く労働者の高齢化は、近年の労災増加に影響を与えています。
60歳以上になると転倒やつまずきによる事故の発生率が高く、身体機能の変化がリスク要因として顕在化しています。
特に建設業や運輸業といった高齢者比率の高い分野では、安全配慮の必要性が強まっています。
労働環境の変化
慢性的な人手不足により、長時間労働や詰め込み作業が多くの現場で常態化しています。
適切な休憩が取れず無理な作業が続けば、集中力の低下や判断ミスを招きやすくなり、事故のリスクが高まります。
こうした背景からも、働き方の見直しが急がれています。
設備や教育体制の格差
零細企業などでは、安全設備の更新が遅れているケースも見られます。
古い設備が使われたままになっている現場では、特に新人や外国人労働者が危険を正しく把握できず、初歩的な事故を起こしやすくなります。
安全文化を根付かせるためにはマニュアルを整えるとともに、日常の声かけや現場での実践を通じた継続的な意識付けが欠かせません。
法改正の動きはどうなっている?

労働災害を減らすため、労働安全衛生法はこれまでに何度も改正されてきました。
代表的な改正の一つが、リスクアセスメントの義務化です。
これは作業に伴う危険を事前に洗い出し、回避策を講じた上で作業を実施することを求めるものです。
また2015年にはストレスチェック制度が導入され、身体的な災害だけでなく、メンタルヘルスへの配慮も求められるようになりました。
このように労災の定義や管理対象が広がり、現場における安全管理の範囲も変化しています。
主な改正内容と施行時期をまとめました。
| 改正内容 | 施行時期 | 概要 |
|---|---|---|
| リスクアセスメントの義務化 | 2016年(平成28年)6月 | 化学物質の危険性を評価し、対策を講じることが義務化 |
| ストレスチェック制度の導入 | 2015年(平成27年)12月 | 従業員50人以上の事業場で年1回のストレスチェックが義務化 |
| ストレスチェック義務の拡大 | 2028年(令和10年)までに施行予定 | 小規模事業場も義務対象とする法改正が進行中 |
| 化学物質管理の強化 | 2025年(令和7年)4月1日 | 対象物質の追加や保護範囲の拡大など規制が強化 |
企業独自の取り組み

近年、法令遵守は当然のことながら、企業が自主的に安全対策を強化する動きが広がっています。
労災事故は企業の信用やブランドイメージに直結するため、安全管理が経営課題の一つとして捉えられるようになっているからです。
例えば、朝礼での安全確認や作業前のリスク予測活動(KY活動)、ヒヤリハットの共有といった日常的な取り組みが定着しつつあります。
また、大手企業を中心に協力会社も含めた安全教育を行い、現場全体の意識向上を図る事例も増えています。
マニュアルだけに頼るのではなく、誰もが安全に働ける風土づくりが求められている時代といえるでしょう。
まとめ
労災事故のうち、死亡災害は長期的に減少傾向にある一方で転倒や腰痛といった日常的な事故は横ばい、あるいは微増しています。
法改正により安全管理の枠組みは整いつつありますが、それだけで十分とは言えません。
現場で働く一人ひとりの意識と、企業全体で「安全を当たり前にする」文化を根づかせていくことが大切です。
労災ゼロの実現に向けて、日々の現場から継続的な改善を重ねていきましょう。

株式会社G-place 設備資材事業グループ
📞03-3527-2992
受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
■関連ニュース記事
2024/12/10 労働新聞社
【お役立ち資料箱】高所作業のリスク再検討を 安全措置が不十分で死亡災害も 長野・松本労基署
2024/09/10 労働新聞社
適正業者登録制創設へ 安全管理の取組みを評価 墜転落災害防止で 仮設工業会
2024/08/09 労働新聞社
【トピックス】高所作業の墜落対策を確認 重点業種で好事例水平展開へ 労働局がパトロール 全国安全週間
2024/08/09 労働新聞社
足場業者に登録制度 労災減少めざし創設へ 仮設工業会
2024/06/21 RSK山陽放送
建設現場ではどんな安全対策を?労災事故が多くなるといわれる夏を前に岡山労働局が岡山市役所・新庁舎の建設現場を視察
2024/04/08 株式会社 流通研究社
厚労省、墜落制止用器具の規格不適合製品を公表
2024/01/29 日本経済新聞
西尾レント、転落防止フック未装着を検知 建設現場向け
2023/12/05 ハーバード・ビジネス・レビュー
労働者を危険から守りたければ、自社だけで安全対策してはいけない

