
高所作業時の事故を「ゼロ」に!
株式会社G-Place 設備資材事業グループの平野です。
弊社では現場での高所事故を防ぐべく、年間のべ50件以上の現場にお邪魔し安全対策のご提案をしています。
この記事では「フルハーネス着用が必要な業種」について解説します!
ぜひご参考にしていただければと思います。
2022年1月より、業種や職場環境によって、フルハーネス型墜落制止用器具の使用に関する特別教育の実施と現場での着用が義務化されました。
しかし、安全帯に関する法改正の通知だけでは、高所作業に従事する全ての職人や事業所がフルハーネスを使用しなければならないと誤解されるケースがあります。
建設業では高さ5mを基準にフルハーネスの使用が原則化されていますが、これを全てのケースに当てはめて考えてしまうと、かえって混乱を招いてしまいます。
例えば、「5m以下であれば使用しなくていい」と誤解し、着用が必要な場面でも使用しないといった危険性があります。
このような問題を解消するには、フルハーネス着用義務化に関する判断基準の正しい理解が重要です。
本記事を参考にして、安全な作業実施を心がけていただければと思います!
作業床の設置が困難な場所(高さ2メートル以上)での作業

フルハーネス義務化を求められる業種は、やはり墜落事故率の多い建設業であることは間違いないのですが、建設業であってもフルハーネスを着用する必要がない現場職人さんも存在します。
フルハーネス着用が完全に必要なのは、「高さ6,75m(建設業においては5m以上)での作業」という状況が前提であり、いわゆる高所からの転落、墜落事故という状況を防止するのが主な目的です。
同じ建設業でも一般住宅の建設が主体の会社であれば、高さ5mを超えるというのは屋根工事などの一部に限られてきます。
一方、柱上作業や屋根上作業、鉄骨上の作業のように高所作業が頻繁にある足場設置業者(いわゆるとび職等)もいます。
いわゆる大工さん等、主に建設業の内側を担当する職人さんにおいては、足場があることによってフルハーネスを必要としないケースも多くなります。
事業者の視点からすると、複数の工事を請け負うという形態の場合であれば、【職種】【作業床の有無】【作業時の高さ】の3点をしっかりと確認しつつ、フルハーネスの着用が必要かどうかを判断していく必要があります。
フルハーネスを着用したから足場が不要というわけではない

労働災害が起こるメカニズムには様々なものが存在しており、一概に「これだっ!」という原因を特定できるというものではありません。
しかし、多くの場合、労働環境が密接に影響していることは否定できません。
そもそも、足場のない現場環境が問題であるという指摘をする専門家も多いのが労働災害防止への課題点でもあります。
ただし、仮に足場を設置しているからといって、それだけで安全が担保されるわけではありません。
労働者の体調管理、注意力散漫などで重大な事故につながる可能性はいくらでも残っているわけです。
まず最初に整えるべきは「現場の労働環境」であり、その中の取り組みの1つが墜落制止用器具の使用である、というのが本筋となります。
労働災害を防ぐための安全対策は、事故リスクのパーセンテージを少しずつでも減らすことが大切です。
そのためには、事業者と労働者の間で「安全対策への意識の齟齬を減らす」ということが重要になります。
高さ5メートル以下、2メートル以上での作業について

以前、「フルハーネスが危険になる!?自由落下と高さ2メートルの壁」という記事でもご紹介しましたが、フルハーネスが必要になる場面とは反対に、フルハーネスが危険を招いてしまう可能性のある状況にも注意する必要があります。
特に判断に悩むのは、6.75メートル以下(建設業で5メートル以下)、かつ2メートル以上で作業をしなければならない環境だと言えます。
できる限り足場を設置するのはもちろんなのですが、胴ベルト型安全帯とフルハーネス安全帯の使い分けも考えておく必要があります。

まとめ
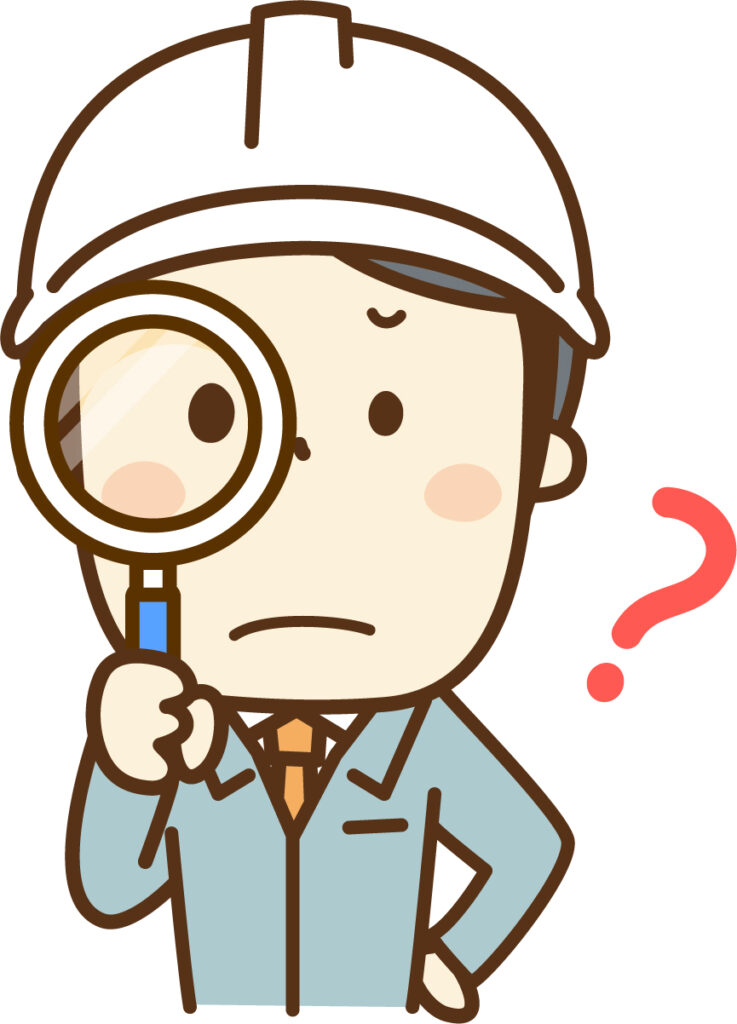
現場で働く人々にとって、自分が所属している会社の安全対策を意識する機会は少ないかもしれません。
しかし、いざ危険な場面に遭遇してしまうと、自分の会社の取り組み方などに疑問が浮かぶことも多いのではないでしょうか?
また、フルハーネス義務化の法改正は、業種や条件によっても適用される範囲が変わるものなので、自分が働いている環境が新しい基準に対応できているかどうか分かりにくい部分は存在します。
特に6.75メートルと5メートルの差は建設業に分類されるかどうかで判断されることになるため、一人親方や小規模事業者は、日本産業分類を参照するなどして自社が当てはまる業種をしっかりと確認しておきましょう。
複数の作業や業務が重なる業種では、場合によってはフルハーネスを適用する必要があるかもしれませんし、その逆もあるかもしれません。
ぜひ機会を見つけて全体的な安全対策を見直してみてください。
また、安全対策についてなにかわからないことや不安なことなどございましたら、お気軽にG-Place にご相談くださいませ!

株式会社G-place 設備資材事業グループ
📞03-3527-2992
受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
■関連ニュース記事
2024/12/10 労働新聞社
【お役立ち資料箱】高所作業のリスク再検討を 安全措置が不十分で死亡災害も 長野・松本労基署
2024/09/10 労働新聞社
適正業者登録制創設へ 安全管理の取組みを評価 墜転落災害防止で 仮設工業会
2024/08/09 労働新聞社
【トピックス】高所作業の墜落対策を確認 重点業種で好事例水平展開へ 労働局がパトロール 全国安全週間
2024/08/09 労働新聞社
足場業者に登録制度 労災減少めざし創設へ 仮設工業会
2024/06/21 RSK山陽放送
建設現場ではどんな安全対策を?労災事故が多くなるといわれる夏を前に岡山労働局が岡山市役所・新庁舎の建設現場を視察
2024/04/08 株式会社 流通研究社
厚労省、墜落制止用器具の規格不適合製品を公表
2024/01/29 日本経済新聞
西尾レント、転落防止フック未装着を検知 建設現場向け
2023/12/05 ハーバード・ビジネス・レビュー
労働者を危険から守りたければ、自社だけで安全対策してはいけない


